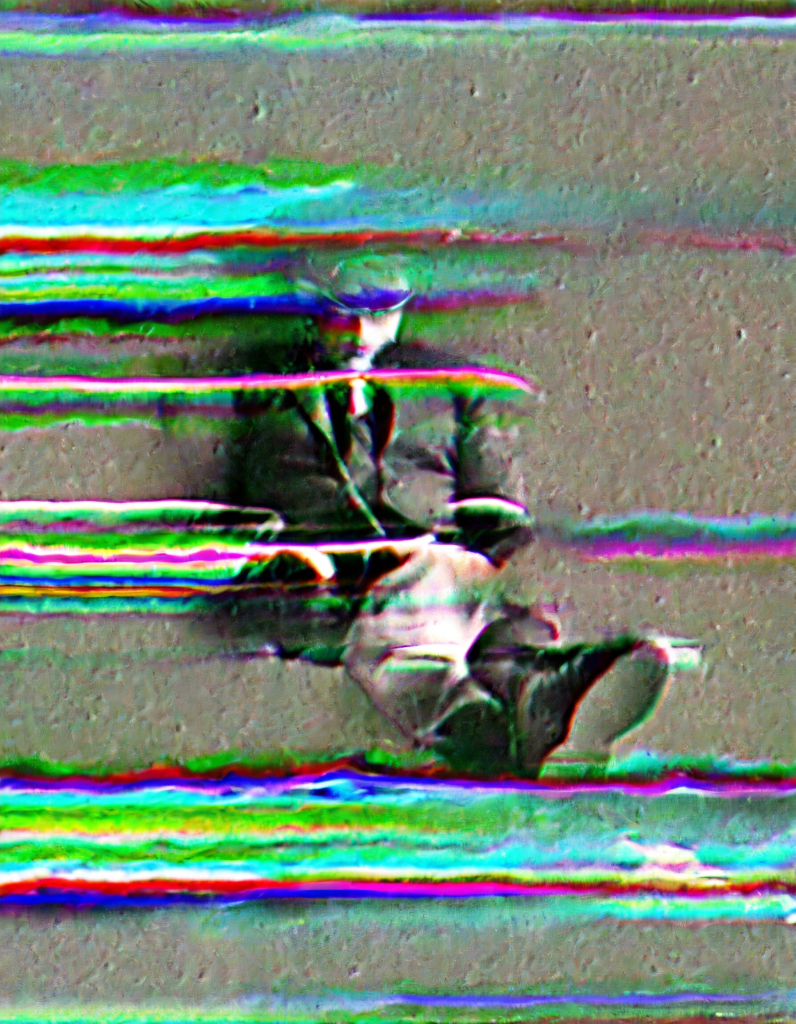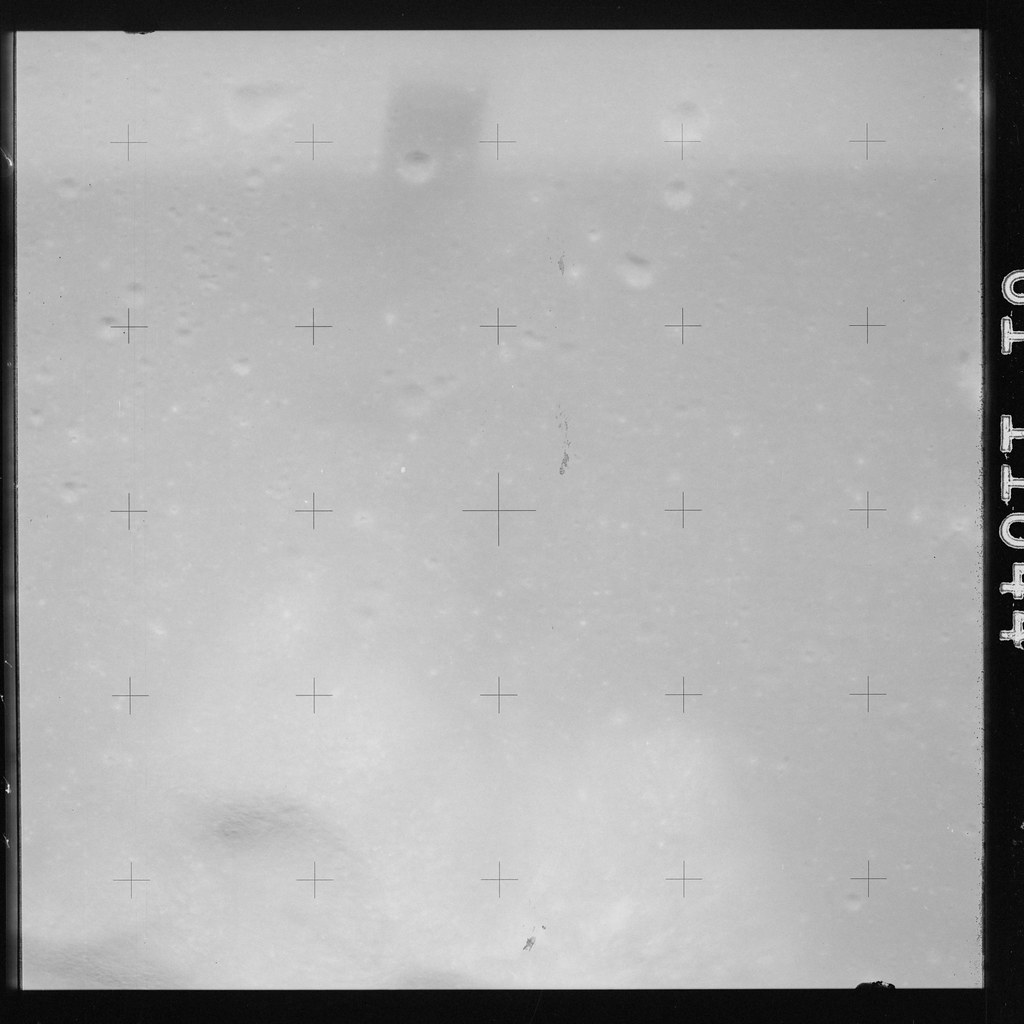__________________________________________________
□何者か
私は皆さんとはだいぶ違う。間違いなく人間なのだが、姿形の話ではなく、何というか、自身の望む望まないに関わらず、起こりうる可能性、行動の可能範囲のようなもの。それが違う。そう思う。もし見下したように聞こえたのであれば気を悪くしないで欲しい。皆さんと同じ点ももちろんある。服装や髪型には拘りがあるし、煙草も吸う。手荷物があり、その中にはいつだって書きかけの記事がある。私も同じ人間なのだから。
いや、そんなことはどうでもいい。私が何者か。それはどうでもいいこと。重要なのは、私がこれまでに出会った多くの人達。有名、無名は関係ない。その人柄、生い立ち、残した言葉。何を体験し、何を成したかにあり、そして絶対に続きがあるということ。
__________________________________________________